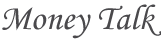上場時の時価総額ランキング(歴代)
上場時の時価総額ランキングです。日本の歴代の大型IPO。初値ベース。1位はNTT、2位はドコモ、3位ゆうちょ銀行です。スナップアップ投資顧問やSMBC日興証券の資料を基に作成しました。
| 順位 | 社名 | 上場時期 | 時価総額(初値ベース) |
|---|---|---|---|
| 1 | NTT | 1987年2月 | 24兆9600億円 |
| 2 | NTTドコモ | 1998年10月 | 8兆8090億円 |
| 3 | ゆうちょ銀行 | 2015年11月 | 7兆5600億円 (自己株式を除くと6兆2991億円) |
| 4 | 日本郵政 | 2015年11月 | 7兆3395億円 |
| 5 | JR東日本 | 1993年10月 | 2兆4000億円 |
| 6 | JT(日本たばこ産業) | 1994年10月 | 2兆3800億円 |
| 7 | リクルートホールディングス | 2014年10月 | 1兆8200億円 |
| 8 | 新生銀行 | 2004年2月 | 1兆7730億円 |
| 9 | かんぽ生命保険 | 2015年11月 | 1兆7574億円 |
| 10 | ソフトバンクモバイル | 1994年9月 | 1兆6220億円 |
| 11 | 第一生命保険 | 2010年4月 | 1兆6000億円 |
| 12 | 大塚ホールディングス | 2010年12月 | 1兆2110億円 |
| 13 | 国際石油開発 | 2004年11月 | 1兆1050億円 |
解説~日本の大型IPOの多くは「国営企業」
日本の過去の大型IPOの多くは、国営企業を民営化したときの株式上場案件である。この点は、アメリカなど海外のIPOの上位ランキングとは大きく異なる。
1980年代の中曽根内閣の民営化
1980年代、中曽根康弘内閣は、日本電信電話公社(現NTT)、国鉄(現JR東日本、JR東海、JR西日本、JR九州)、日本専売公社(現日本たばこ産業=JT)を民営化し、それらの株式を上場した。
小泉内閣の郵政民営化
また、2000年代の小泉純一郎内閣は、日本郵政公社を分割民営化し、日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命が2015年に上場した。NTTドコモは、NTTの連結子会社である。KDDIは、国際電信電話、日本道路公団などをルーツに持つ。
ソフトバンクも旧国鉄の通信部門
時価総額2位のソフトバンク・グループ(SBG)は1981年設立と、比較的若い。ただし、SBGの中核子会社で、2018年12月に上場したソフトバンクの通信事業の歴史は実は古い。元々は旧国鉄の通信部門に起源を持ち、国鉄の民営化時に日本テレコムとして分離。その移動体通信部門がJフォンとなった。英ボーダフォンがJフォンを買収後、SBGがボーダフォン日本法人などを買収し、現在のソフトバンクに至る。ソフトバンクを中心とした国内通信事業は、SBGの営業利益のうち約半分を占める。
民間企業も歴史が古い
日本の時価総額ランキングで現在トップのトヨタ自動車は1895年設立の豊田商店が起源だ。このほか、純粋な民間企業で時価総額が大きい会社も古い企業が多い。例えばソニーの創業は1946年、ホンダは48年と、いずれも70年以上の歴史を持つ。
ファーストリテイリングは若いイメージを持たれがちだが、2019年で創業70年を迎える。法人設立は1963年とは言え、柳井正会長兼社長の父らが、前身のメンズショップ小郡商事を創業したのは1949年にさかのぼるのだ。
体質的な問題
日本には、政府による介入のみならず、自由競争を阻害する慣行が今なお数多く残る。今でも、多くの日本企業は年功序列や終身雇用制を採用する。若者がいくら優秀でも年配者よりも給料が低いといった非合理なシステムでは、グローバル時代に通用するのは難しい。こうした体質が変わらない限り、今後も、日本から世界的なベンチャー企業が生まれるとは考えにくい。
日本流インキュベーション
一方で、歴史的に、日本のインキュベーション(事業創出)方法として、国営企業の民営化や政府資産売却は有効な手段であった。世界でもこれほどまでに政府資産売却、民営化で成功した国はない。
三菱系も国営企業が多い
例えば、三菱マテリアルのルーツは三菱財閥が買収した長崎の高島炭鉱だし、三菱重工業も三菱財閥による国営長崎造船所の買収を起源とする。三菱地所は、東京・丸の内の軍の練兵場を買収し、日本を代表するビジネス街に育てた。新日鉄住金のルーツは官営八幡製鉄所である。
「国鉄→JR」という成功例
民営化企業の中で最も成功しているのはJRである。民営化前の1986年度、旧国鉄の最終損失は1・4兆円であったが、2017年度には上場4社の経常利益は合計で1・3兆円と劇的に改善した。
平成はソニー、ホンダ現れず
株式市場という視点では、昭和の時代と比較して、平成は不振であったことは否めない。その最大の原因の一つは、昭和期のソニーやホンダのような世界的に活躍できるベンチャー企業が生まれなかったことである。長年、ベンチャー企業を育てることは日本の大きな政策課題であった。
ベンチャー育成は苦手
しかし、「貯蓄から投資へ」「東京の国際金融センター化」同様、結果として実現していない。これだけ長期間にわたって実現しないものが、突如として実現すると考えるのは現実的ではない。よって、ベンチャー育成など苦手な分野よりも、得意な分野に注力する方が合理的だ。
羽田空港や東京メトロの民営化とIPOを
かつての三菱財閥、そして現在のSBGがその好例であるように、政府資産の買収を活用して成長した企業は少なくない。現在も、民営化し、かつ新規上場(IPO)すれば高収益企業になることが期待できる事業は多い。
日本政策金融公庫や住宅金融支援機構も
例えば、羽田空港、成田空港、高速道路、国立競技場、東京メトロ、都営地下鉄、都営バスなどである。さらに、政府系金融機関も有力なIPO候補となる。具体的には、日本政策金融公庫や住宅金融支援機構である。
再度、政府がリーダーシップをとって、民営化、政府資産売却を加速し、日本型インキュベーションを成功させることが次の時代に求められる。